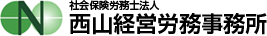従業員の休職について、どう対応してよいのかよくわからない
従業員から「会社が休職を指示するのなら、私本人の同意が必要だ」と言われてしまいました。
また別の機会に別の従業員に休職命令を出そうとした際には、勤務中に具合が悪そうなのは明らかなのに「就労は可能」という内容の診断書を提出してきました。
「休職には本人の同意が必要」と主張する従業員への対応
最初の「休職には本人の同意が必要」と主張する従業員への対応のケースです。
そもそも休職は使用者の人事権の行使として行われるものです。それが休職命令の(法的)性質であり「従業員の同意」は不要です。正確には、一方的な休職命令の根拠は「就業規則」ですので(+労働契約に基づく使用者権限)、就業規則上の根拠が必要になります。もし就業規則に休職制度の記載がない場合には、その方との「個別の同意」が必要となります。
<具体的な対応手順>
就業規則の確認:休職に関する規定が適切に整備されているかを確認
休職命令の発令:医学的根拠に基づき、書面で正式に休職命令を通知
制度説明:休職は労働契約上の権利でもあり、治療に専念することの重要性を説明
<規定例>
〇「・・・次のいずれかに該当するときは、休職とする」
〇「・・・次の各号に該当する場合には、会社は休職を命する(ことができる)」
×「・・・次の各号に該当し、休職願を提出した場合は・・・休職とする」
明らかに体調不良なのに就労可能とある診断書を提出する従業員への対応
2つ目の「明らかに体調不良なのに就労可能とある診断書を提出する従業員への対応」のケースです。
もしそのまま働かせてしまったら、会社にも従業意にも芳しくない状態です。
会社には安全配慮義務があります。診断書の内容と実際の状況に乖離がある場合には、慎重に対応する必要があります。無理に働いて傷病が悪化してしまい、障害や死亡に至った場合、労災や安全配慮義務違反(訴訟)の可能性が出てきます。
また、そもそも本人が医師に業務内容を適切に説明できていない可能性も大きいのです。
会社として行うべき対応方法
第1段階:追加の医学的判断の要求
- 主治医面談を行い、具体的な症状や業務への支障について、あらためて意見を求める。会社から業務内容を説明すると、判断が「就業不可」に変わることもある。
- 産業医がいる場合には産業医による面談の実施
- セカンドオピニオンとして他の医療機関での診断書提出を求める
第2段階:就労可能範囲の詳細確認
- 診断書に「どのような業務なら可能か」の具体的記載を求める
- 勤務時間の制限や業務内容の制限について医師の意見を確認
- 可能であれば、症状悪化時の対応方法についても明記を求める
第3段階:適切な就労環境の検討
- 診断書の内容に基づいた業務調整や配置転換の検討
- 時短勤務や在宅勤務などの配慮措置の実施
- 定期的な健康状態の確認体制の構築
<留意事項>
- すべてのやり取りを書面で記録しましょう。また、症状や業務への影響も客観的に記録し、医師との面談記録や診断書の保管を行います。
- 就業規則は整備しましよう
休職制度や健康管理に関する規定を明確化して「休職事由と手続き」「診断書提出の義務」「治療専念義務」を必ず明記します。