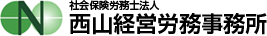有期雇用契約時の離職票の区分がよくわからない
契約社員など、有期雇用契約の社員が契約を終了する際に、円満に契約終了したと思っていても、そのつもりはないのに「事業主が原因」=「解雇扱い」となってしまうケースがあります。
そこで有期雇用契約の場合の「離職票区分早見表と注意すべきポイント」を示します。
以下は、雇用保険の喪失原因がどのように分類されるかをまとめた表です。
喪失原因「3」が事業主理由=解雇扱い

この表の見方のポイントは4つです
①通算雇用期間3年未満の場合(上の表)は、事業主原因による離職にはなりません。(=通算雇用期間が3年以上となった場合に注意が必要)
②通算雇用期間が3年以上となった場合(下の表)、「雇止めの通知」を出さないと「同意書を受け取った」か「本人が希望しなかった場合」以外は
→「事業主の原因(喪失原因3)」(解雇扱と同じ)となります。
※「雇止めの通知」は、最後の契約更新時に「これが最後の契約です」と伝えてあったのか?書面としても残っているか?も重要です。
③本人が更新を希望した場合や、会社が更新希望の確認をしなかった場合には 「一般受給資格者(給付制限はあり)」にはなりません(~他のいずれかになります)
④本人が更新を希望しなかった場合は、いずれの場合でも「一般受給資格者」です(ただし本人に給付制限ある場合とない場合あり)。
【用語の説明】
- 特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇など会社都合により再就職の準備期間がないまま離職を余儀なくされた失業手当(失業保険)の受給資格者のことです。特定受給資格者に該当するかどうかは、離職票やそのほかの提出書類をもとにハローワークが判断します。 - 特定理由離職者
以下の理由で退職した人が該当します。
・労働契約の更新を希望したが更新されなかった人
・家庭の事情や家庭問題などのやむを得ない理由で、自己都合によって退職した人
一般受給資格者よりも受給条件が緩和され、一定期間の失業手当(失業保険)を受給できない給付制限期間が設けられずに失業手当(失業保険)が受給できます。
なお、「特定理由離職者」の中でも労働契約が更新されなかった場合は、給付日数が特定受給資格者と同じく手厚い給付が受けられます。一方、やむを得ない理由で自己都合によって退職した場合は、一般の受給資格者と同様の給付日数になります。