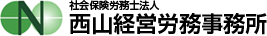職員が監督署に、上司のパワハラでうつ病になったと労災申請をした
<労災申請と会社の安全配慮義務について>
顧問先のお客さま企業のところに、以下の文書(「労災保険給付請求にかかる関係資料の提出について(依頼)」添付1)が届いた際、当事務所が新任のご担当者からのご照会に対応したメール(の一部)です(~実際のケースですが、特定されないよう一定の加工をしています)。
〇〇 さま
いつもお世話になっております。
労働基準監督署から送られてきたこの書類(調査用紙)と関連事項のご説明いたします。最近今回のようなケースは散見され、ご説明をする機会は初めてではありません。
1 まず、労災給付(今回の療養補償給付:5号用紙)は、過失や無過失、といった要因には関係がなく、
A 業務遂行性(=仕事中に)
B 業務起因性(=仕事が原因で)
のAとB 2つの要件が満たされれば、ほぼ必ず支給されます。なので、
仕事中に仕事が原因の「ケガ」の場合には、必ず支給されます。
2 しかし、それが「仕事での病気」となると話が別であり、ハードルが上がります。というのは、仕事での「けが」はよくありますが、仕事での「病気」というのはあまりないので、労災の対象になる「病気の種類」がはじめから決まっており(下記)、ケガのときのようには簡単にはいきません。
具体的には、次のような精神障害が挙げられます。
- 症状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分[感情]障害
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格及び行動の障害
- 知的障害<精神遅滞>
- 心理的発達の障害
- 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
- 詳細不明の精神障害
3 ましてや、今回の職員の方の主張のような「会社からのパワハラが原因でうつ病になった」・・という申出の精神疾患の類をすべてとりあげて労災認定をしていたら、労働基準監督署は日本中ですごい数の労災給付をしなければならなくなってしまいます。
ゆえに「精神障害の労災認定」P10 添付2記載のフローチャートのように厳格な認定への流れがあります。要約すると、以下の①②③の条件をもクリアしないと認定されないことになります。
特に③の「業務以外には要因がないこと」の証明はかんたんにはできないというか、証明しにくいので、結果として申請の多くは却下されてしまいます。
①労災認定の対象となる精神障害を発病していること
まず、発病している精神障害が労災認定の対象のものであるかどうかがポイントになります。
労災認定の対象となるのは、国際統計分類の第5章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害のうち「認知症や頭部外傷などによる障害」と「アルコール・薬物による障害」を除いたものです。先にあげた表のことです。
②発病前6ヶ月の間に業務による強いストレスを受けたこと
2つ目に、精神障害を発病する前のおよそ6ヶ月の間に、仕事が原因と考えられる強いストレスを受けていることも基準のひとつです。
(強いストレスを感じたのが6ヶ月より前である場合は、精神障害との因果関係を判断することが難しくなるとされています)
「強いストレス」の要因となる出来事については、厚生労働省が例示している内容を参考にして判断していくことになります。
たとえば「業務に関連し、他人を死亡させた」「1ヶ月間におおむね160時間を超えるような時間外労働を行った」などは「特別な出来事」に該当し「強い心理的負荷を受けた」と判断されます。
「特別な出来事」がない場合は「具体的出来事」(「精神障害の労災認定」P5~8 添付2)に記載された内容の中から、当てはまるものや近いものをあてはめ、心理的負荷の強度を評価して判断をします。
③業務外の要因により精神障害を発病したとは認められないこと
「仕事とは関係のない要因による心理的負荷で精神障害を発病していないか?」が3つの判断基準です。
(「精神障害の労災認定」P9 添付2)にあるような出来事があったとき、その心理的負荷の強度はどの程度のものかで労災の対象になるかを判断します。
厚生労働省の評価表によると「自分が重い病気やケガ・流産をした場合」は心理的負荷の強度がⅢ、「収入が減少した場合」はⅡ、「子どもの入試や進学があった」はⅠというように評価されています。心理的負荷の強度が高い出来事があった場合、認定はより慎重に検討されることになります。
これらの1から3により、判断するのは監督署の方ですし、今回は、会社(上司)からご本人にパワハラがあったかどうかの確認の調査でもあるので、会社として、事実を誠意をもって回答すべきです。
しかし、上記の1から3を考慮すれば(社内調査の結果、多少の行き過ぎがあったという判断になることもありますが、ではそれが)即=パワハラなのか、ましてや労災認定されるレベルになるのか・・というご懸念には及ばないと思います。
ただし、「精神障害の労災認定」P8 添付2に記載のある「長時間労働」や「ハラスメント」があったと認定されると、労災認定される可能性はかなり高まります。御法人の場合には、調査の結果、この2つとも「なし」ということが明らかになっていますので、そのことも合わせて説明していく必要があります。
4 ここからは別の観点「損害賠償」のお話です。労災のことだけであれば、会社が悪いということにはなりません。先に記載の通り、労災には過失の有無も関係ありません。
ご存じのとおり、労災の申請書(5号用紙)には、「事業主の証明」欄があり、
「現認」=事故現場で見たとか最初に報告されたことなどを記載する様式になっています。しかし、メンタルの病気の場合には、けがのように、発病(病気になった)瞬間の現場を見ようにも見られないので、会社は現認ができない=「仕事による病気についての証明」などはできないのではないか?ということを、前任の〇〇さんにお伝えをしました。
ご存じかもしれませんが
労災療養補償給付申請(5号用紙)は、会社の押印(証明)を書かなくても、本人と医師欄だけで、労働基準監督署は受付をしてくれます。
ただしあとから「なぜ会社は事業主証明をしないのか、その事情を聴きたい」 ということで、監督官からのヒアリングが入ったり、今回のように「調査用紙」が送られてきます。
5 注意が必要なのは、会社(社長)が、「労災給付なんてどうせ国が払うのだし、会社がお金を払うわけではないので、負担にならない」と安易に考えて、そのケガや病気の経緯や内容をろくに確認もしないで、労災の申請用紙に、会社の証明をしてしまうことです。会社に責任がないのにリスクだけ負ってしまうことにつながりかねません。
労災申請がOKになってしまうと
=会社が労災を認めた
=ということは、「会社が自分の非を認めた・・」と論点がすりかわり、
具体的には、
会社側に「不法行為」や「安全配慮義務違反」があったとして、
労災申請をした方が弁護士さんに相談して、会社に「損害賠償請求」を起こすということにつながりかねません(弁護士さんの話では、日本中でこのような裁判が散見されるとのことです)。
労災申請がOKになるかどうかは、あくまでも最初に書いた
A 業務遂行性(仕事中に)
B 業務起因性(仕事が原因で) の2つのことでしか決まりません。
しかし、
民事=損害賠償請求事件の裁判官は、
労災支給決定の要件(2つのこと)を、あまりよくわかっていないということはない・・・と信じたいのですが、
「会社が証明や押印したということは、会社に安全配慮義務違反があったと会社が認めたのだろう」と解釈し、本来は2つ要因で決まるはずの「労災」と、「安全配慮義務(違反)」とをごっちゃにして、(会社はきちんと安全配慮義務をしていたにもかかわらず、していないのだろうとの)不当(?)な判決を出し、会社が数百万から数千万の損害賠償金を請求されてしまう・・・可能性が出てきます。
そのようなことにならないように、もし労災かどうかの確信がないのなら、法人内の合意形成なしに、うかつに「事業主証明」をしない方がよい・・というお話も(当方の弁護士さんの受け売りですが)、〇〇さんにはいたしました。
6 最後になりますが、今回の対象の方は、今までは自分が「パワハラ行為の加害者側」として他の職員を退職に追いやったり、メンタルがやられるようなことをさんざんしてきた方であるという過去の実態や経緯、その対策として人事異動・降格したことを契機に、今度は急に「被害者としての主張をしはじめた」といったことも、監督署にはご説明しておいた方がよい・・ ということも伝えました。
以上になります。