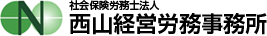年金事務所の調査にどのように対応したらよいかわからない<社会保険調査対応について>
顧問先のお客さまのところには、たまにこのような文書が届きます添付1添付2。年金事務所からの調査実施の文書です。そこで、この「社会保険調査」についてご説明します。
1 社会保険調査の概要と目的
年金事務所から「全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金被保険者の資格及び報酬の調査の実施について」ないしは単に「総合調査」という名の書類が届きます。
これは、社会保険の適用状況を総合的に確認する定期的な調査で、法律上は原則4年に1回該当することになっています。
調査の主な目的は以下の通りです:
- 社会保険の未加入者がいないかの確認
- 標準報酬月額が実際の支給額と乖離していないかの検証
- 各種届出書類の未提出がないかのチェック
- 保険料控除が適正に行われているかの確認
調査で確認される主な項目
年金事務所の調査では、以下の内容が詳細に確認されます。ただし、調査対象者リストが交付され、対象者が限定されることも多いです。
| 確認項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 賃金関係 | 賃金の締日・支払日の確認 |
| 事業所情報 | 事業所や事業主の登録情報変更の有無 |
| 加入状況 | 社会保険の未加入者の有無 |
| 届出状況 | 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の未提出確認 |
| 資格取得・喪失 | 取得時期・喪失時期の適正性 |
| 報酬額 | 資格取得時や現在の報酬額と実際の支給額の乖離確認 |
準備すべき書類
調査に必要な書類は事前に郵送で案内されますが、一般的には以下の書類が必要です。
| 書類名 | 確認内容 |
|---|---|
| 賃金台帳 | (全)従業員の賃金支払状況 |
| 出勤簿・タイムカード | 労働時間・出勤状況の確認 |
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 労働条件の詳細 |
| 労働者名簿 | 従業員の基本情報 |
| 退職関係書類 | 退職日確認のための退職届等 |
| 就業規則 | 労働条件に関する社内規程 |
| 有給休暇取得申請書 | 有給休暇の取得状況 |
| 源泉所得税納付書 | 税務関連書類 |
2 調査実施に関する留意事項
・調査の拒否について
調査を断ることは原則できません。調査を受けることは法令で定められています。拒否した場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(ただし、年金事務所は労働基準監督署とは異なり強制力を持ち合わせていません)。
・書類提出について
書類の提出も法令で義務付けられており、提出を拒むことはできません。拒否した場合も同様の罰則が適用されます。
・立会者について
社長でなくても立会は可能です。社労士の同席も認めてくれます。要は社会保険手続きの内容を把握し、調査に対応できる担当者であれば問題ありません(その方が役所も助かるようです)。
・調査日程の変更
日程変更は可能です。書類準備が間に合わない、担当者が不在などの事情がある場合は、事前に年金事務所の調査担当者に連絡して相談してください。年金事務所の方でも予定が詰まっていることが多いので、月退位(翌月)で変更されることも多々あります。
・身分確認
調査員は顔写真付きの身分証明書と立入検査証を携帯しています。企業側から求めれば提示してもらえます。
・調査の所要時間と頻度
調査時間:一般的に30分〜2時間程度(事業所規模や担当者により変動しますが日をまたぐことはありません。ただし、上司の判断等を仰ぐなどで、まれに持ちかえることはあります。
・調査頻度:約4年に1回の定期調査
(新規適用事業所は加入から約1年後)
・加入漏れが発覚した場合の対応
もし調査で加入漏れが発覚した場合には加入届出の拒否はできず、年金事務所から加入手続きの指示(要請)があります。また(拒否の経験はありませんが)年金事務所権限での加入手続きが行われることもあるとのことです。
・一時的な労働時間の変動について
契約内容と異なり「一時的に労働時間が長かった場合」、以前はその旨を説明すれば納得してもらえることが多かったですが、最近は「2か月間、労働時間がオーバーしていたら「加入して(すぐ喪失してほしい)」と言われることも多いかと思います(~今その人はすでに労働時間が短くなっているから・・は通用しない)。超過が一時的であったことの証明として、調査後2〜3か月分の出勤簿や賃金台帳の提出が求められる場合もあります。
3 最近の年金事務所調査の傾向について
制度改正の影響などから、最近の年金事務所調査には、次の4つの傾向が見受けられます。
①賞与届の厳格化
年金事務所の方は、よく「私たちには『毎月の報酬』か『臨時の報酬』の2種類しかない」という主張をされます。
その背景には、適正な保険料徴収の強化があります。従来は曖昧に処理されがちだった臨時の収入(決算賞与、業績賞与、各種手当の一時払い等)について、年金事務所は「報酬」として扱うべきものを厳格に判定し、賞与支払届の提出を求めるようになっています。
年末の賞与支給ができず、せめてもの寸志で「もち代一律1人2,000円」を交付したり、給与明細の中で「特別手当30,000円」として支給したりすると、それらは賞与扱いになり、賞与届の対象になります。
②取得時標準報酬月額の厳格化
取得時の標準報酬月額決定の厳格化は、入社時の過少申告防止が主な狙いです。
従来は企業側の申告をある程度信頼していましたが、現在は雇用契約書や賃金規程との整合性、同職種・同等級者との比較などを詳細に確認し、実態と乖離がある場合は積極的に訂正を求めています。特に試用期間中の賃金設定や、各種手当の取り扱いについて厳しくチェックされています。
③月額変更届の徹底
わずかな固定的賃金の変動でも月額変更届の提出を求める傾向は、随時改定(月変)制度の適正運用を徹底する方針の表れです。
年金事務所は、企業が「少額だから届出不要」と判断しがちな昇給についても、制度上は金額の大小に関わらず固定的賃金の変動があれば検討が必要であることを強調しています。
これにより、将来的な保険給付の計算基礎となる標準報酬月額の正確性を確保しようとするあらわれという方もいます。たとえ100円の昇給であっても、「月変」に該当すれば見逃されません。
④適用拡大対応の強化
2022年10月、2024年10月と段階的に進む社会保険適用拡大への対応が、調査の重点項目となっています。
特に従業員数101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業では、短時間労働者の適用漏れがないか厳格にチェックされています。また、資格取得届の被保険者区分コードの記載ミス(一般被保険者「0」と短時間労働者「1」の区別)についても細かく指摘されるようになっています。
<調査方針変化の背景>
これらの傾向の根底には以下の要因があります。
- 年金財政の健全化:適正な保険料徴収による収入確保
- 制度改正への対応:適用拡大等の新制度の確実な実施
- デジタル化の進展:データ分析による効率的な調査対象選定
- 企業の意識向上:加入漏れが減少したことで、より詳細な部分の指摘に目が向いた
| 調査項目 | 対応のポイント |
|---|---|
| 賞与関連 | □ 臨時収入の性質を明確に整理 □ 報酬と賞与の区分基準を社内で統一 |
| 取得時決定 | □ 雇用契約書と実際の支給額の整合性確認 □ 各種手当の取扱い基準を明文化 |
| 月額変更 | □ 固定的賃金変動の定期的なチェック体制構築 □ 少額でも制度上の検討は必要と認識 |
| 適用拡大 | □ 短時間労働者の労働条件を定期的に確認 □ 被保険者区分コードの正確な記載 |
4 調査手法のデジタル化トレンド
企業側のデジタル化対応として、法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)については、データ保存が法的に認められており、調査時には「必要事項が直ちに明らかにされ、かつ、打ち出しができる状況」を整備していれば問題ありません。
年金事務所側の対応変化についても、以下の傾向が見られます。
| 従来の調査 | 現在のトレンド |
|---|---|
| 全書類の紙ベース提出要求 | 画面確認での対応増加 |
| 一律的な書類準備指示 | 指摘対象者のみ印刷要求 |
| 年金事務所未保有情報も企業に要求 | 既保有情報は要求減少 |
調査効率化の背景
年金事務所の調査では、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、労働者名簿などの確認が行われますが、これらの書類について「労働基準監督署などの調査時や行政機関から閲覧や提出などを求められたときに「必要事項が直ちに明らかにされる状態」であれば、必ずしも事前の紙ベース準備は不要とされています。
実務上の留意点
ただし、調査対応時の準備として
①画面表示での確認に応じられるよう、システム環境を整備しておく
②指摘事項が発生した場合には即座に該当データを印刷できる体制を維持する
ことに留意が必要です。
※法定保存期間の遵守は変わらず重要
<参考>保存期間文書一覧(5年以下のもの)
監査報告・会計監査報告(5年)
従業員の身元保証書、誓約書など(5年)
健康診断個人票(5年)
雇用保険の被保険者に関する書類(4年)
労働者名簿、雇入または退職に関する書類(3年)
災害補償に関する書類(3年)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する書類(2年)