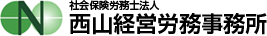納税が手元にキャッシュフローを増やすという考え方<キャッシュフロー経営について>
「積極的な納税は、かえって手元にキャッシュフローを増やすことにつながる」という考え方は、多くの税理士さんが推奨しています。
単なる節税ではなく、法人と個人の資産形成を総合的に捉えた戦略です。
主に「経営者の役員報酬」と「法人税」のバランスに関わるものですし、キャッシュ不足による倒産を防ぐことにつながります。
蓄財(キャッシュフロー)の仕組み
この仕組みを理解するためには、以下の2つのポイント(重要)です。
- 法人税は個人所得税・住民税より税率が低いこと:
法人の所得にかかる法人税、事業税、住民税を合わせた実効税率は、通常30%台です。一方、個人の給与所得にかかる所得税と住民税は、所得が上がれば上がるほど税率も高くなる累進課税です。役員報酬として個人に支払う額を増やしすぎると、個人の税負担が法人税を上回る逆転現象が起こり、結果として手元に残る金額が少なくなります。 - 法人の内部留保は、将来の成長投資やリスクに備えられること:
利益を役員報酬として全額支払うのではなく、法人に利益として残す(内部留保する)ことで、その資金を設備投資、人材採用、M&A、または不測の事態に備えるための資金として活用できます。これにより、法人の安定的な成長と、経営者の将来的な所得増加の基盤を築くことができます。
蓄財のフロー
具体的なフローは以下の通りです。
- 適正な役員報酬の設定
- まず、経営者自身の生活費を賄える最低限の適正な役員報酬を設定します。無理に報酬を高く設定せず、個人の税負担が過度に重くならないようにします。
- 法人に利益を留保する
- 役員報酬を抑えた結果、法人の税引前利益が増加し、支払うべき法人税が増えます。
この段階では「納税額が増えた」と感じますが、その分、法人の手元にキャッシュが残ります。このキャッシュが内部留保となります。
- 法人のキャッシュを有効活用する
- 法人に残ったキャッシュを、将来の事業拡大や福利厚生に投資します。
例えば、高額な生命保険(法人契約)に加入することで、万一の際の保障を確保しつつ、保険料を損金に算入できる場合があります。
また、退職金規程を整備し、将来的に大きな金額を無税で受け取れるように準備することも可能です。
- 最終的な資産形成
- これにより、法人の収益力は向上し、安定した事業基盤が構築されます。
将来的に役員退職金という形でまとまった金額を受け取ることで、個人の資産形成を図ることができます。
この退職金は、給与所得とは異なり税制優遇が大きい退職所得として扱われるため、手元に残る金額が非常に大きくなります。
目先の節税にとらわれず、法人全体のキャッシュフローと将来の資産形成を総合的に考えることで、結果として手元に多くの資金を残すことができます。そして何よりも重要な点は、キャッシュが枯渇した=倒産した ということを避けるための戦略であるということです。